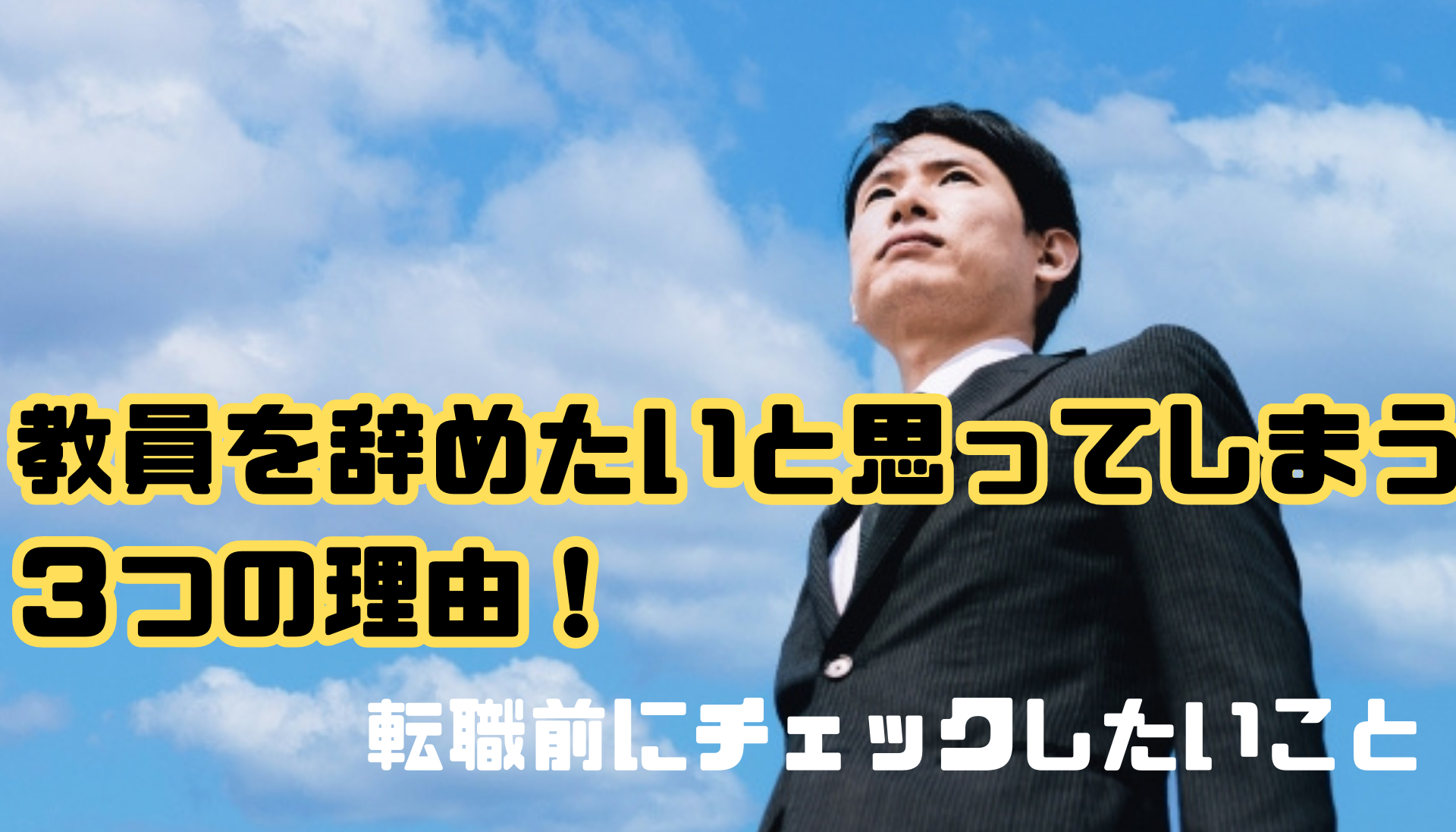学校の先生になることが夢でした。
一生、学校の先生として働くつもりで就職しました。
でも、実際に仕事を始めてみると、大変なことも多く、辞めたいと思う事が増えています。
世の中の人たちは、気軽に転職ができていいな・・・。

仕事も忙しくて大変・・・。
今が踏ん張りどきなのか、体調を崩す前にやめた方が良いのか、迷い時です。
みんなどんな時に、やめてるんだろう・・・。
先生を辞めて起業をした私の元には、多くの相談が寄せられています。
色々な先生が色々な想いで仕事をされているので、
考え方の違いや理想の求め方の違いから、別の道を選ぶことも当たり前です。
辞めたいと思っても大丈夫。
ただ、先生という職業柄、同業以外への転職をする人が身近にいないという方も多いでしょう。
実際にどんな理由で先生を辞める人が多いのでしょうか。
また、どんな理由で、他職種への転職を決意する人が多いのでしょうか。
今回は、教員を辞めたいと思ってしまう3つの理由について、ご紹介していきます。
【筆者】 株式会社 Life Value Up 代表取締役 辻 みつる あなたの「教員 辞めたい」を叶えます[st_toc]【経歴】 東京で教師を10年間経験後、 「教員が嫌になり」 退職。 独立起業し、ビジネスを0から学び始める。 2023年 現在 3つの学習塾の経営をしながら、 セミナー事業、コンサル事業、婚活事業など、 他事業にも拡大。 現在、アルバイトを含め 10人以上の従業員を抱える会社の代表。 今一番注力していることは、 「教員のセカンドキャリアサポート」 自身の経験をもとに、 教員を辞めたいと思っている方が その不安を解消して一歩踏み出せるようサポートしています。
教員が辞めたいと思ってしまう理由:①人間関係
教員という職業柄、「児童・生徒」との信頼構築は当たり前に必要になりますが、その他にも「同僚の先生方」や「保護者」との関係性も重要です。
人事移動の時期が来れば、解決することもありますが、あまりに状況が拗れてしまって、精神的に厳しい場合は転職に向けて、準備をしてみるといいでしょう。
転職をしたとしても、同じ状況を作ってしまっては、意味がありません。何が、どのように辛いのかを整理する際に、次の文を参考にしてみてください。
児童・生徒との関係性
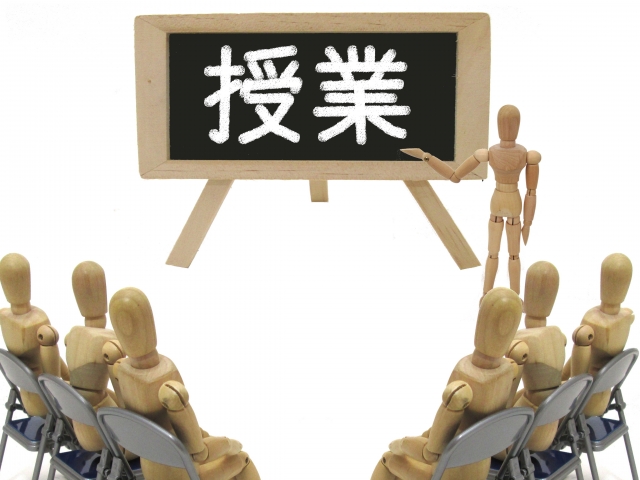
色々な子がいるので、先生であっても、対応がしやすい子・苦手な子がいるのは当たり前。
それでも児童・生徒との信頼関係を築き、成長に導くのが先生としての腕の見せ所でもあります。
ただ、児童・生徒たちは思春期の精神的に不安定な時期でもあります。
児童・生徒たちは、1つずつ色々なことにぶつかりながら大人に近づいている時期であるので、不安定なのは当たり前のこと。
しかし、それに常に対処しなければならないことは、先生にとって楽なことではありません。
時に、状況が悪化していじめに発展する事だってあるので、児童・生徒との関係を辛く思ったとしても仕方がありません。
特定の児童・生徒に対処することが難しいですか?
それとも全般的に児童・生徒に対峙することが難しいですか?
ゆっくりで構いません。
「転職をするとしたら」と考えて、現状を整理してみましょう。
他の先生方との関係性
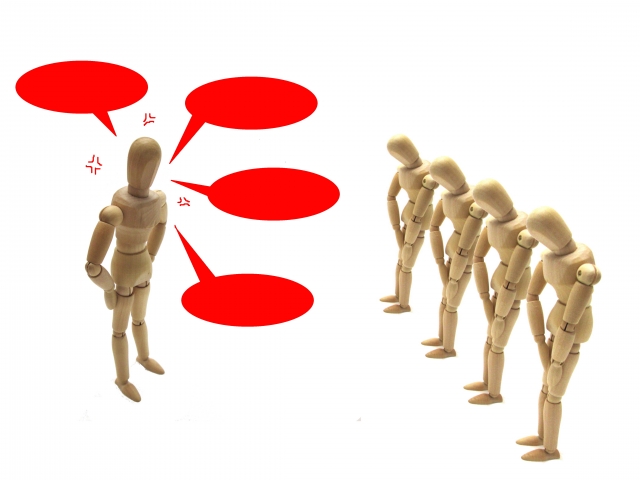
教室では先生は1人であることが多いですが、学校では他の先生方と協力する業務は多くあります。
職員室というコミュニティは小さな社会です。
もしトラブルが発生したら、その先生との関係性だけでなく、
職員室の居心地が悪くなる事だってあります。
そのため、他の先生方との関係性も、波風立たないようにしたいものです。
誰もが波風が立たないようにと思っていたとしても、その中の1人と相性が悪かった場合、
うまく信頼関係を築くことができないこともありますね。
関係をつくるのが大変だな…と思う人は、特定の人に対してだけですか?
それとも仕事の特性やルールによるものですか?
これらも、退職時までに、分析してみると良いでしょう。
保護者との関係性

日頃、児童・生徒と接していたとしても、背景には保護者がいます。
学校として、児童・生徒の学びを伸ばすためには、保護者の協力を得なければなりません。
そのため、先生方は保護者との信頼関係の構築を目指しますが、それは簡単ではありません。
なぜなら、保護者は先生方と同じ大人ではありますが、年代も、仕事も、根本の考え方も、異なるからです。
保護者も仕事を持っているので、連絡がつく時間帯も、人それぞれだったりします。
中には、先生や学校への意見をかなりキツい口調で言ってきたり
かなり難しい要望を言ってきたりする保護者もいますし、
保護者によって対応を変えざるを得ないというのが現状でしょう。
児童・生徒だけでなく、保護者に対しても、個別に対応しないといけないのであれば、得意不得意があって当たり前です。
先生という仕事が辛い、辞めたいとあなたが感じるのは、どのような点ですか?
どんな保護者に対応するのが、嫌だと感じますか?
他に転職した場合、同じ人に出会う事は、ほとんどないと思いますが、同じような状況になる事だってあります。
どんな人が苦手で、どんな対応が嫌だと感じるのかを考えてみましょう。
教員が辞めたいと思ってしまう理由②:体力不足

同じ先生という職種であっても、私立or公立、小学校or中学校or高校によって、勤務条件が異なりますね。
ただ、どの先生であっても共通するのは、児童・生徒のためと思うと、仕事が増えていつの間にか残業が当たり前になってしまうということ。
実際に、文部科学省の調査によると、教員(小・中学校)の1日あたりの学内勤務時間は下記の通りです。
一般的なサラリーマンでは8時間勤務が多く、比較すると、教員の勤務時間が長いことがよくわかります。
| 小学校の教員1日当たりの学内勤務時間 | 中学校の教員の1日当たりの学内勤務時間 |
| 11時間15分 | 11時間32分 |
ここに書かれた調査対象の時間は、日常の授業時のものです。「部活動」「学校行事」などがあれば、通常業務に加えて、学校内意外で仕事をしているはずです。
実際のところは、もっと勤務時間は長いとす考えると、体力的にキツくなっても当たり前です。
他の先生方が当たり前とこなしていたとしても、大変だと感じても良い時間数です。
労働安全衛生総合研究所 医学博士の高橋さんは、残業時間が月100時間、または2カ月ないし6カ月の平均で80時間超の場合、健康に害が現れる基準だと、プレジデントオンラインで紹介しています。
この月100時間残業という値は、月20日で働いたとすると、1日5時間の残業です。
学校行事で、土日も勤務することがある教員で考えるとどうでしょうか。
参考:1日何時間残業すると健康を害するのか 1日4時間残業でうつ症状が倍に #プレジデントオンライン
データで見たとしても、教員の仕事が体力的に厳しい事はよくわかります。
体力的に辛いという場合は、転職のためにプライベートの時間を割くというよりも、
まずは体力の負荷をリセットすることをお勧めします。
この場合の転職については、また別の記事に詳しく書きたいと思います。
教員が辞めたいと思ってしまう理由③:将来が不安

日本は、少子高齢化が進み、「高齢社会」となってきています。
2025年には30%が高齢者になるという予測もあるほどです。
子供が少なくなると、必要となる学校や教員も減ってしまうため、
教員としての明るい未来が見えないという話もよく聞きます。
さらに、コロナの影響もありオンライン授業も広がっていることも、不安を煽ります。
児童・生徒に直接教えることよりも、より上手い授業をする先生の動画の方が、選ばれることが起きています。
少子高齢化に加え、e-ラーニングの普及も、明るい未来が見えなくなる理由のひとつです。
プログラミングなど、今までになかった教科も増えているだけでなく、教員に求められるスキルが増えていることから、特に30代の先生方はスキル不足から危機感を覚える傾向にあります。
どんな職種であっても、スキルアップは常に必要ではありますが、今までの業務で培っているスキルは必ずあるはずです。
今、不足しているスキルだけではなく、
先生として習得してきたスキルに目を向けてみて下さい。
この分析が転職を前にした際、役に立ちます。
転職の方法については、また別の記事に書きますね。